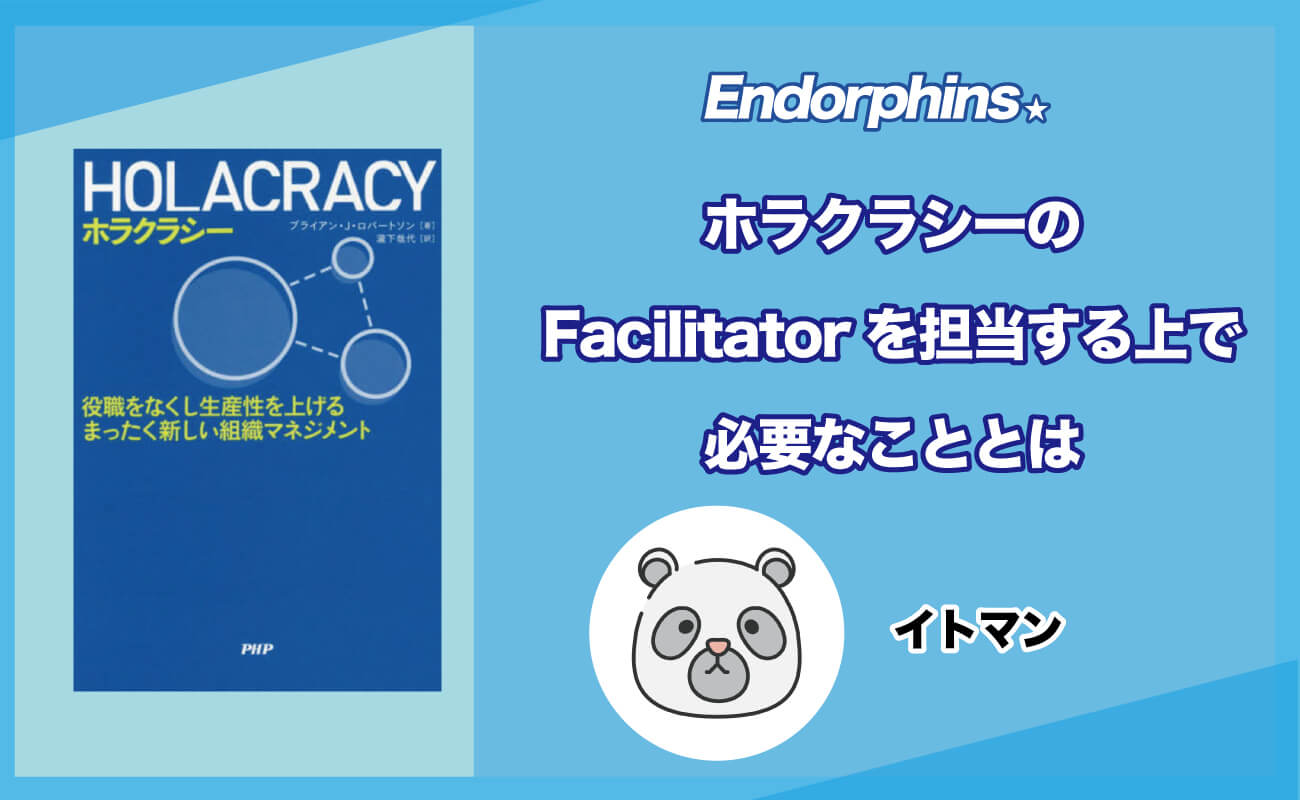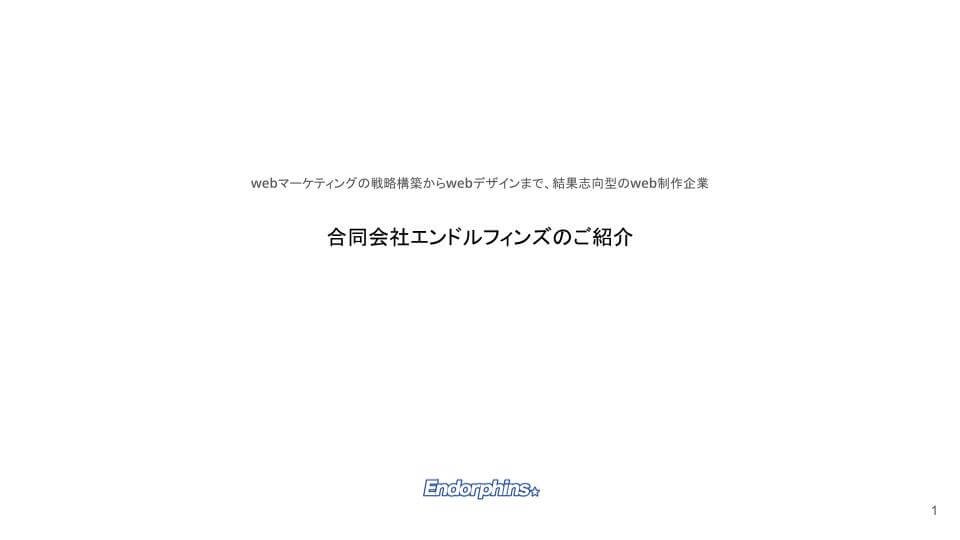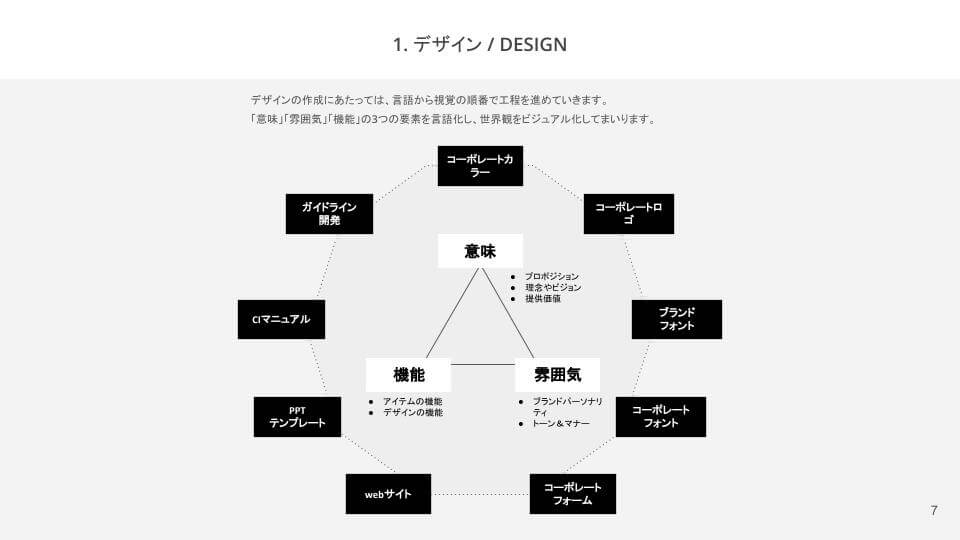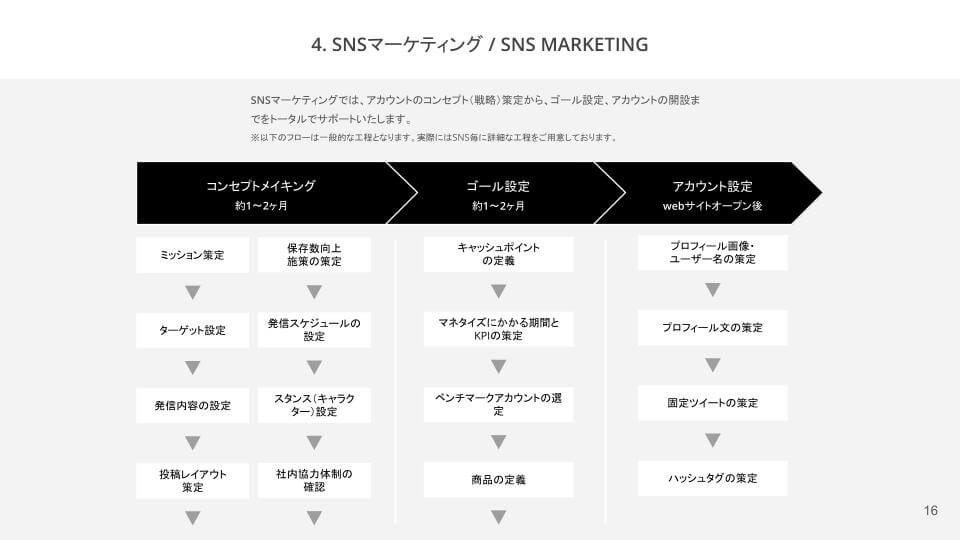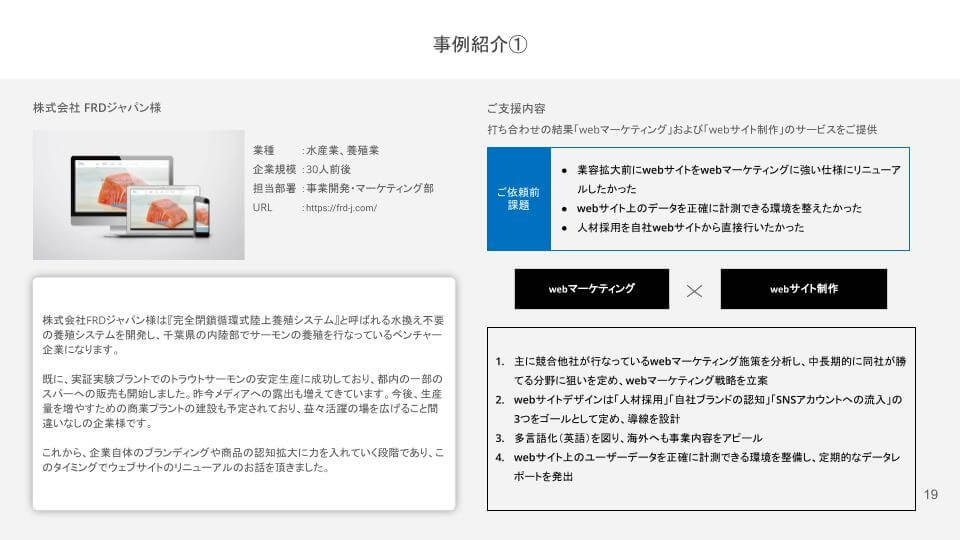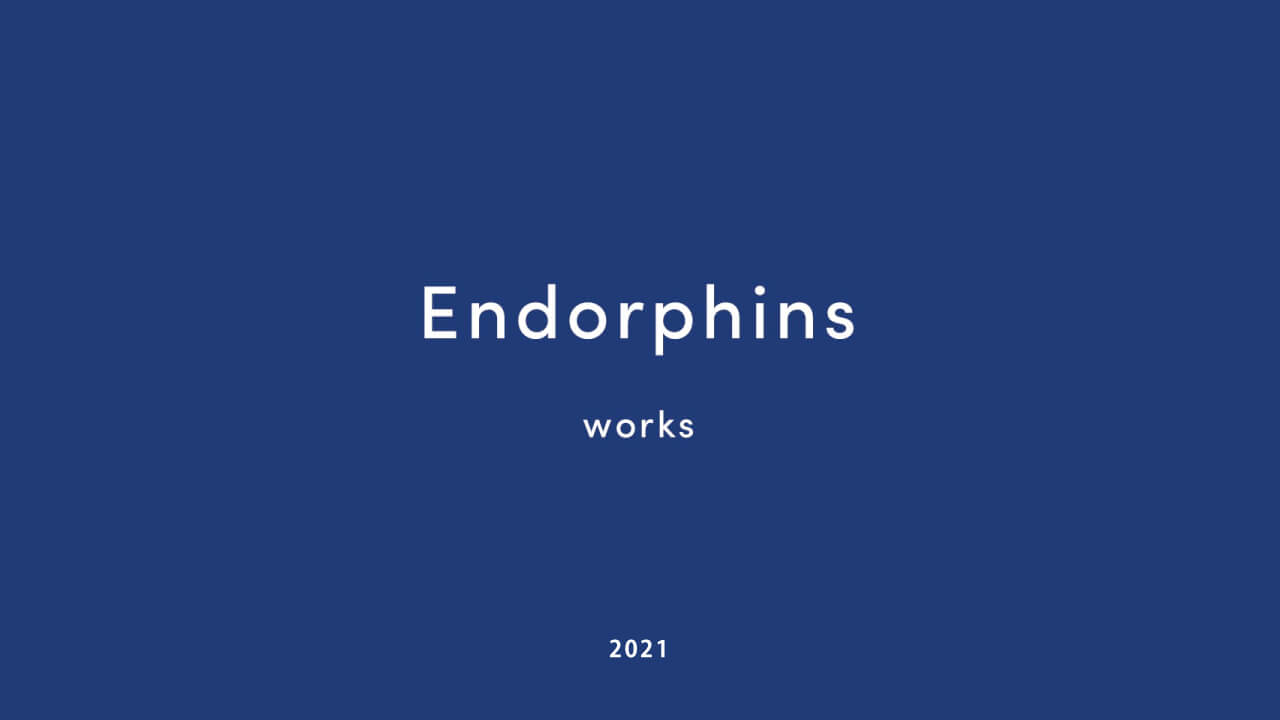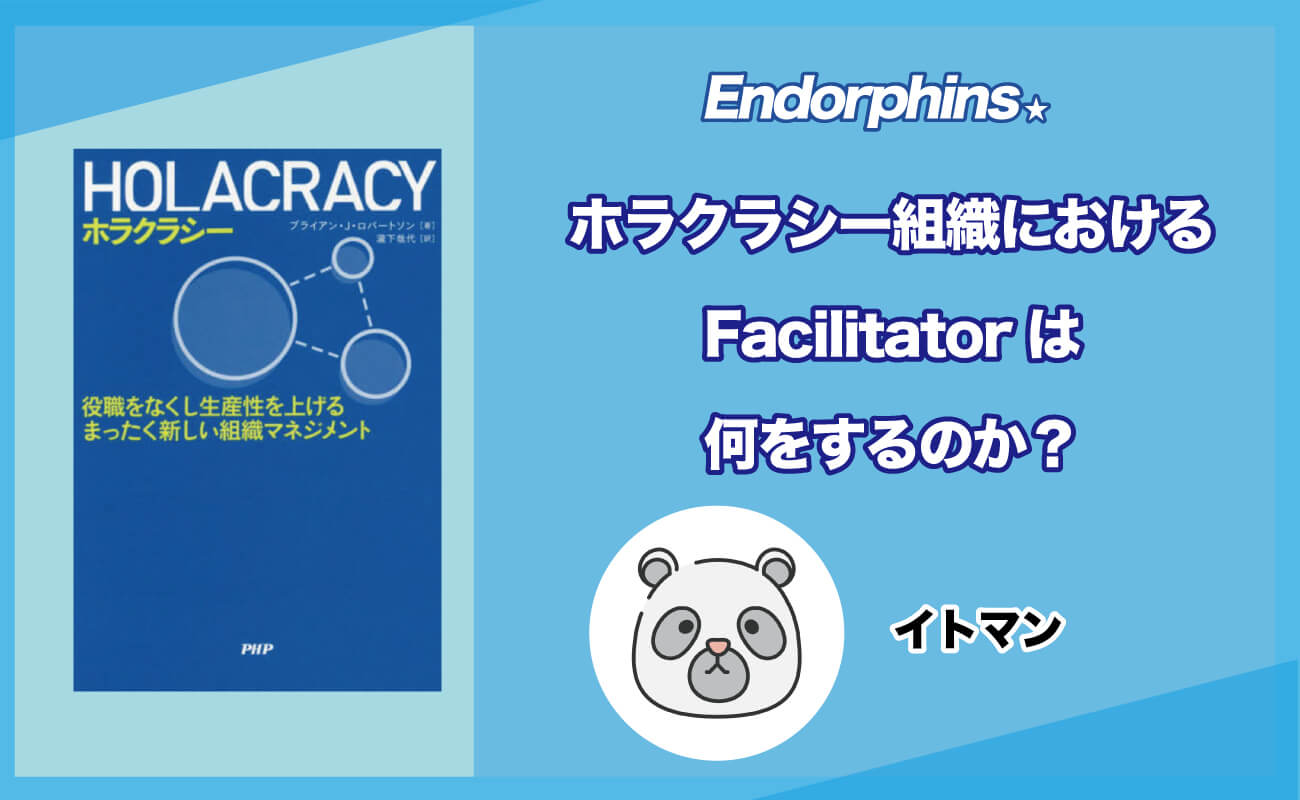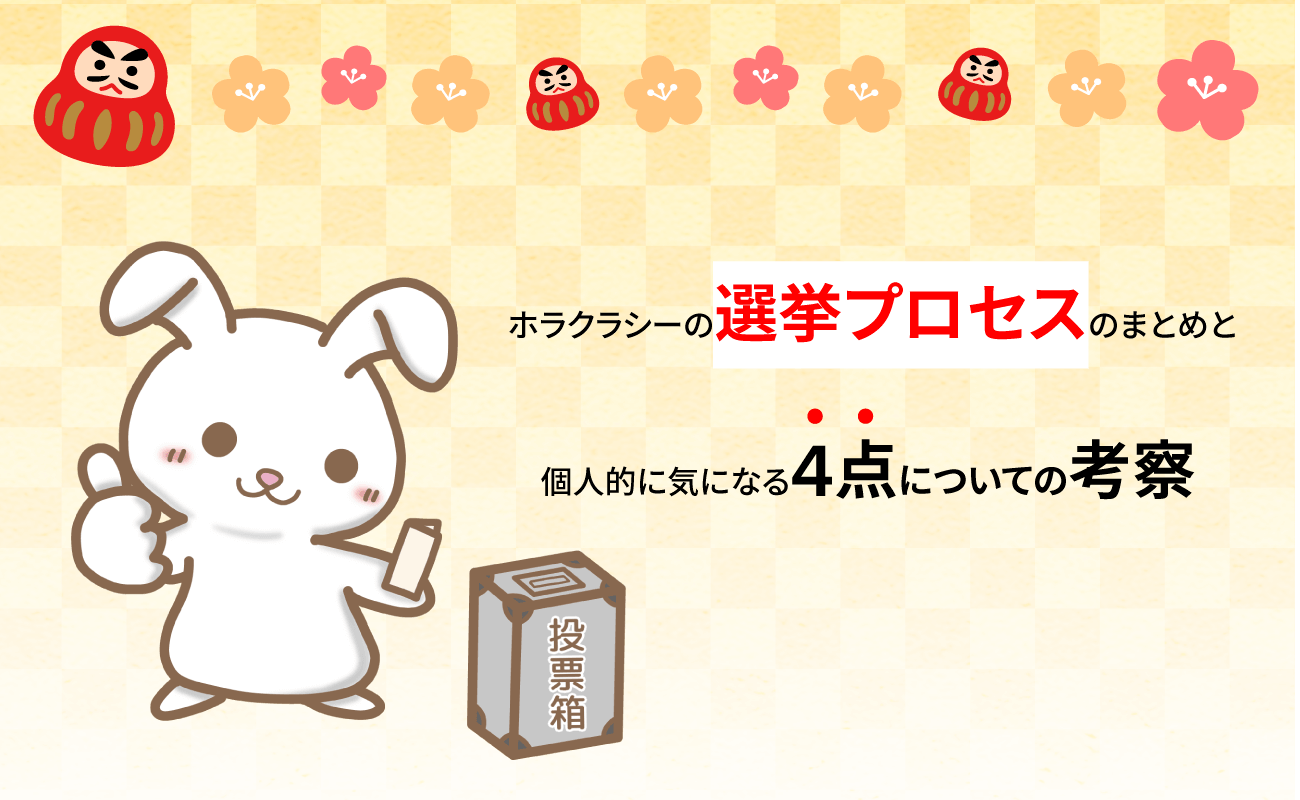皆さんこんにちは。エンドルフィンズCreative loverのイトマンです!
前回の記事「ホラクラシー組織におけるFacilitatorとは」ではホラクラシーにおけるFacilitatorとはどのようなロールであるのか説明をしました。
第2回は、前回の内容を踏まえた上で、私の経験も踏まえながらFacilitatorをする上で必要だと感じた要素をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください!
前回を読まれていない方は、まずはそちらを確認してくださいね。
目次
ホラクラシーのFacilitatorに必要なこと

週1回のミーティングを半年ほど経験したことで、少しずつですがFacilitatorに必要なことがわかってきました。
その中で特にFacilitatorがすべきだと感じたことは次の3つです。
①誰よりも ガバナンスミーティング・タクティカルミーティングのプロセスを理解すること
②ホラクラシー型での進行経験を積み重ねること(RPでも可)
③過去に起きたイレギュラーな知見を蓄積すること
どの項目もごく当たり前のことばかりですが、自分の想定以上に「①理解」・「②経験」・「③蓄積」が重要だと感じました。
特に「②経験」が大切で、事前に想定をしていても、従来型の認識に引っ張られて気がついたらプロセス違反になっていることも経験しました。
せっかくですので、実際のミーティングで経験した例を紹介したいと思いますが、理解しやすくするためにホラクラシー組織のミーティングプロセスの一部を簡単にですが説明します。
なお、もっと詳しいミーティングの進行方法については、次回以降の記事で紹介しますのでそちらもぜひご確認ください。
ミーティングでは各フェイズにおいて、していい行動としてはいけない行動がホラクラシー憲法にて明確に規定されています。
例えば、メトリクスレビューというKPIなど最新データの報告を行うフェイズでは、報告者以外の参加者は詳細を知るための「質問」をすることは可能ですが、「提案」や「話し合い」、「合意」をすることはできません。
そのためFacilitatorは参加者の質問が「本物の質問」なのか、それとも「質問を模した提案や合意」ではないのかを見極める必要があります。
この辺りがFacilitatorの腕の見せ所であり、難しい点でもあります。
これから紹介する例もこの点で従来の認識を排除できずに失敗した例になっています。
Facilitatorでの失敗事例
<HP作成のプロジェクト進捗報告のフェイズでの一幕>
Aさん
「・・・。PCデザインの進捗は以上の通りです。」(報告)
Bさん
「レスポンシブデザインの進捗はどこまで進んでいますか?」(質問)
「クライアントからPCデザインのOKが出てから取り掛かる予定です。」(返答)
「OKをもらう前から取り掛かった方がいいですか?」(質問を模した合意確認)
「クライアントにまとめて見せたいので取り掛かって欲しいです。」(合意)
一般的なミーティングであれば特に違和感のない一幕にも思えますが、ホラクラシー組織のミーティングでは「合意」をすることはできません。
今回であればAさんが「質問を模した合意確認」をした時点で、Facilitatorがすかさず「プロセス違反(質問ではなく合意)」であることを指摘する必要がありました(自分はすぐには指摘ができず、Bさんの発言を許してしまいました)。
ではホラクラシー組織として、Aさんは「いつまでにレスポンシブデザインを完成させればいいのか?」という疑問をどのように解決したらよかったのでしょうか。
もし、Aさんがアサインされているロールに「デザインの完成期限を決める」権限がある場合、そもそもAさんが期限確認をする必要はなく、ロールの権限で最適な期限を設定すれば問題ありません。
また、その最適な期限の設定をするためにAさんの持っている情報で足りないのであれば、普段から公開されている情報を確認することで解決すればよいのです。
もし、「情報が公開されていない」や「担当のロールがわからない」などの問題(ホラクラシーでは「歪み」という)が判明したのであれば、アジェンダ(歪み)を処理するフェイズで議題にあげれば問題ありません。
次に、Bさんがアサインされているロールに「デザインの完成期限を決める」権限がある場合ですが、Aさんが疑問に思った時点でBさんは必要な情報を開示できていない状態、つまり歪みが生じています。
ですので、Aさんはアジェンダ(歪み)を処理するフェイズで議題にあげれば問題ありません。
いずれにしても、Aさんは「プロジェクト報告」のフェイズで確認する必要はなかったことがわかると思います。
そして、Facillitatorはこの点を踏まえて以下のように行動すべきでした。
①プロセス違反(質問ではなく合意)であることを指摘する
②「情報不足による歪みがあれば、処理フェイズで提案するように」と伝える
③すぐに次の質問がないか確認する(無ければ次のプロジェクト確認に移る)
なお、今回の実例ではデザイナーであるAさんが気になって先に質問(を模した合意)をしていますが、Bさんの方がクライアントとの関係性を考慮して、Aさんに「〇〇までに作って欲しい」と合意を迫ってもおかしくない場面でもありますので、Facilitatorは注意が必要です。
まとめ
Faclitatorが今回紹介した例を毎回許してしまいプロセスが形骸化してしまうと、「短時間で課題(歪み)を解決する」というホラクラシーの良さが損なわれてしまいます。
そうならないためにFacilitatorには「プロセスの遵守」と「プロセスのチェック」が責務として設定されているのです。
そして、その責務を果たすために「理解」・「経験」・「蓄積」をしっかりと行っていくことが必要です。
これまででFacilitatorの役割などを確認してきましたが、記事に頻繁に登場したガバナンスミーティングやタクティカルミーティングがどういったミーティングなのか疑問に思った方も多いと思います。
次回は Facilitatorがガバナンスミーティング・タクティカルミーティングのそれぞれでどのように進行するのかプロセスの確認をしながら、ガバナンスミーティングやタクティカルミーティングとはどのようなミーティングなのか説明していきたいと思います。